子どもの療育について、私の経験とともに以下にまとめてみました。
療育とは
主に発達に遅れがあったり、特性のあるお子さまに対して行う、医療と教育を組み合わせた支援や指導のことです。一人一人の発達や特性に合わせた関わりを増やし、本人の力を引き出しながら、将来の自立や社会支援を目指します。
子どもが発達障害かも?と感じたら
まずはかかりつけの小児科に相談してみましょう。そのうえで、発達検査が可能である児童精神科を受診します。また地域の保健センター、児童発達支援センターなどでも相談できます。
一歳半健診や三歳児健診で相談してみるのも良いでしょう。
最近は発達障害の認知度が高まり、受診者数が大幅に増加しています。そのため、初診の予約が非常に困難です。予約が取れても、受診は半年後…などめずらしくありません。
主な療育内容
- 感覚統合療法
日常生活の中で感覚(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚・前庭感覚・固有受容感覚など)を上手に処理して使えるようにするためのアプローチ。遊びや運動を通じて感覚をバランスよく統合できるように促す。生活や学習、人との関わりがスムーズになることを目指す。
- 認知行動療法
小さな目標を設定し、出来たらたくさん褒め成功体験を積むなどして、考え方や行動に働きかけて心の状態を改善する。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)
他者との関わり方や自分の気持ちを上手に伝えるなど、社会で必要なコミュニケーションや対人スキルの練習。
- 音楽療法
手遊び歌やリズム遊びなど歌や音楽を通して、心や体の状態を整え生活の質や発達をサポートする。
- 運動療法
鉄棒遊びやトランポリン、ボール遊びなど身体を動かすことを通じて体幹の安定、感覚統合、自己コントロール力を育てる。
- 作業療法
子どもが「生活する力」を身に付けるための支援。ブランコ、トランポリン、積み木、パズルのほか着替えなどの日常生活の練習。
療育はどこで受けられる?
- 児童発達支援センター(未就学児対象)
0歳〜就学前で、発達の遅れや障害がある子ども。
- 放課後等デイサービス(小学校〜高校)
6歳〜18歳までの障害や発達に特性がある子ども。
- 医療機関の発達外来やリハビリ
発達の遅れや特性が気になる子ども。0歳〜高校生まで。病院による。
早期療育の大切さ
子どもの脳はまだ成長過程にあるため、柔らかい状態です。この柔軟性の高い時期に療育を始めると、新しいことを吸収し、支援の効果が出やすいといわれています。
私の子どもは2歳の時に、発達性協調運動障害と診断されました。
しかし、主治医から3歳を過ぎると脳がある程度固まってしまうので、柔らかいうちに療育を始めましょうと言われました。
それから小学校に上がるまでの間、週2〜3日ほど親子で療育に通いました。
とにかく不器用でコミュニケーション能力の低い子でしたが、大学生になった今では友達も出来て日々楽しそうに過ごしています。
とはいえ、焦る必要はありません。子どもの特性は、100人いたら100通りです。
その子にあった支援の方法を見つけ、無理なく続ける環境が大切です。
早期療育は「治す」ためでなく、その子の持ち味を生かして、暮らしやすくすることが目的です。
おわりに
子育てをしていると色んな悩みが出てきます。それが子どもの発達のことになると、なかなか周りに相談できなかったり、育て方が悪いせいではないかと、自分を責めてしまいがちです。
しかし、大切なのは一人で悩まないことです。療育で出会った保護者の方々は、それぞれ悩みを抱えていても笑顔の絶えない素敵な方ばかりでした。子どもの成長を、皆我が子のように喜んでくれました。悩みを話すことで、私もずいぶん心が軽くなりました。
療育はもちろん子どものためではありますが、私自身が救われた部分がとても大きく、かけがえのない思い出になっています。
子どもの成長という大きな山に、一緒に寄り添いながら、たまには一休みしながらゆっくり登っています。
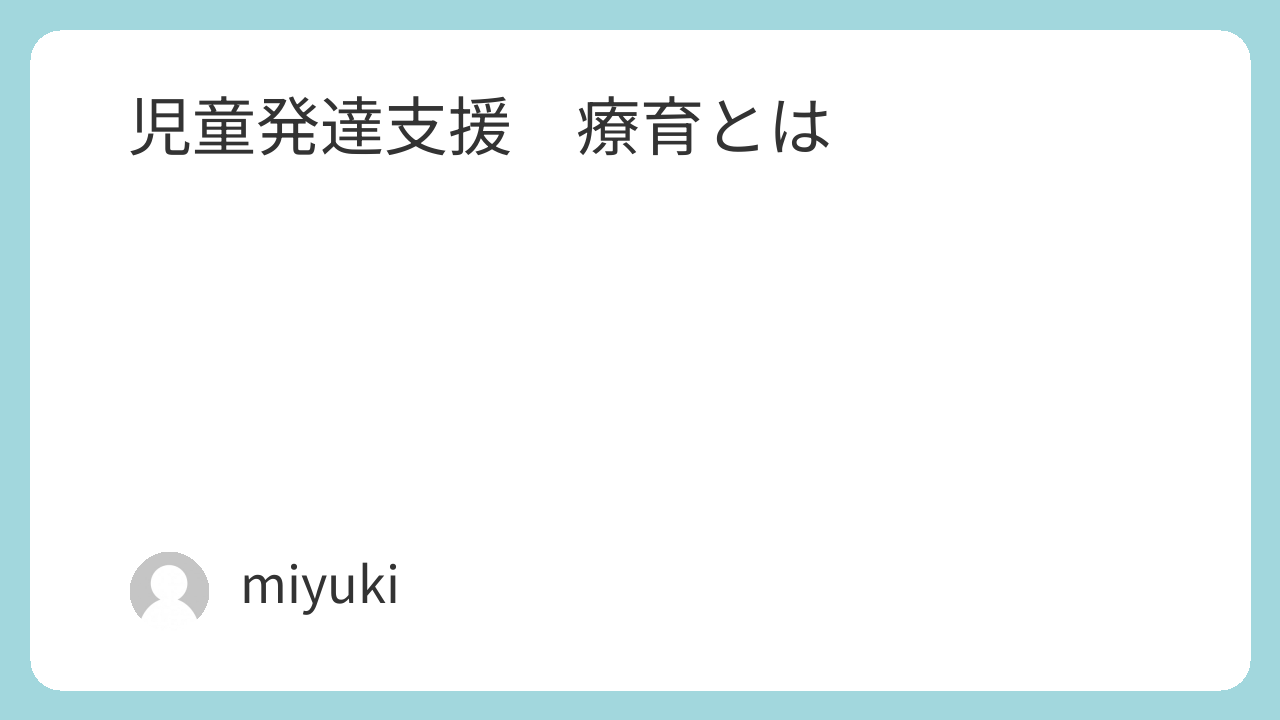
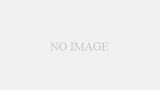
コメント